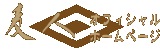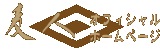す ず め (2000年秋・処女作)
『我と来て遊べや親のない雀 一茶』
もちろん通夜も葬式もない。
霊柩車ではなく、死体搬送業者の黒いワゴンが拘置所の裏門に手配された。
美代は遺体を引き取り、そのまま火葬場へ直行した。
死刑囚の遺体を引き取りに来る遺族は少ないと言う。
「そんなものか」
と、美代は思う。
世間に顔向けならんと、お父さんは事件の半年後、縊死を以って償い、
もちろん親戚縁者も、今後一切関わってくれるなと断りを入れてきた。
ほんとうに何もかも失い、とっくに希望も夢の欠片もないけれど、
誰でもない、自分の胎を痛めて産んだ一人息子。
世間から、鬼よ、冷血な犯罪者よと烙印は押されても、
とにかく死刑執行でその罪を贖った我が子の亡骸、
どうして放棄できようか。
ワゴンの中で美代はおそるおそる棺の蓋を開いた。
「類をみない残虐非道な殺人!」
最終論告で、鷹の眼鋭く検事に糾弾された息子の死に顔。
それを我が一生の罪として、脳裡にしっかり刻む覚悟もあったが、
いよいよ灰と化す前に、やはり今生の別れを告げたかった。
絞首刑という思いこみから、苦痛に歪んで無残な顔を想像していた。
ところがその表情は、いかにも重い十字架を下ろしたような安堵に溢れ、
薄化粧でもするのだろうか、血の気さえ感じる。
「賽の河原で待っておくれ」
しぼり出したように、低くこもった声が思わず出た。
事件後、小学教師夫婦のつましい家庭はもろくも瓦解し、
それからの十八年、美代にとっては終わりのない悪夢を見ている歳月であった。
地方へ逃げず、東京の町を転々と移り住んだ。
大都会では、一見周囲が事件や他人のことに、
おおかた無関心であるように思われ、
それが重い自責の念の呪縛から、自分をいくらか救ってくれた。
とはいえ、ずっと息を潜めて、病院や寮の賄婦をしながら生きてきたのだ。
昔ピアノを弾いていたしなやかな白い指も、今では醜く赤く腫れている。
美代はその指のすべてを、そっと息子の頬に添えた。
どうしてだろう、涙も出ない。悲しみもない。
ただただ息子の死に顔に、
不思議な懐かしさと、いとおしい感情ばかりがつのる。
「どうしてだろう・・・」
焦点のぼけた美代の目に、
墨絵のように淡く濃く、拘置所面会室での日々が浮かんだ。
美代は過去すべての面会日、一日たりとも欠かさずに拘置所を訪れた。
母としての愛もあったが、息子とともに贖罪する意識はより強かった。
しかし息子は遂に最後の最後まで生みの母に心を閉ざし、
かたくなに寡黙で、よそよそしい振りを崩さなかった。
それは当初美代にとって、事件そのものより衝撃的な現実であった。
生みの母を冷たく疎んじる、我が子の深い心の闇。
美代は危うく精神のバランスを失いそうになった。
が、何としても息子の刑の執行までに、
その闇底に沈んでいる汚物の正体を見極めたい。
仮にも教師という職業を経験した女ではないか。
その切実で悲痛な思いが、
美代の正気を紙一重のところで、ずっと今日まで支えてきた。
息子との数え切れない面会。
それは我が子に、血の通った会話を一切拒否された母の、
自らを審判する法廷でもあったのである。
ところが最後に会った日、それも刑務官が面会時間の終了を告げた直後、
息子が椅子から立ち上がりざま、
いつもとまったく様子の異なる口調で叫んだのだ。
母に向けて言ったのかどうか、それはわからない。
宙を睨むように天井を見上げ、底抜けに明るい声で、
「チュンチュク すずめがないている」
と、叫んだのである。
それがあまりに唐突だったので、美代は誰の声かと我が耳を疑った。
「何ですって」
激しい動悸が胸を襲い、遠い過去の苦い思い出が、一瞬美代の記憶に甦えり、
くらくらと目眩を感じた。その記憶を確かめるように、
もう一度、息子の背中に呼びかけた。
「ね、何と言ったの!」
すると彼はクルッと振り向き、おそらくありったけの声を振り絞って、
「チュンチュク すずめがないている、チュンチュク すずめがないている!」
と、同じ言葉をただ繰り返し怒鳴りつづけた。
刑務官が慌てて制止にかかったが、
息子は体をきりもみさせながら抵抗し、なお叫び続け、
駆けつけた二人の屈強な男に取り押さえられ、ようやく部屋から出て行った。
帰ろうとする美代に、面会担当の刑務官が、やれやれといった顔で、
「今朝、一人執行されましてね」
と、洩らした。
工事現場の反響音にも似た鈍重な耳鳴りが、
しばらく美代を襲いつづけ、時が止った。
ようやく動悸が静まり、我が子の叫びを反芻しつつ拘置所を出た。
来た時強く降っていた雨は上がり、突き抜けるような青空に目が眩んだ。
銀杏の枯れ葉が風に舞い、美代の首筋をそっと撫でて地に落ちた。
それから十日後、もうすぐ四十になる、我が子の死刑執行の報せが来た。
指に底なしの冷たい触感がひろがり、美代は我に返った。
目を閉じた地蔵にも似て、息子の顔は平安に満ちている。
かつて美代が、毎晩添い寝で見つめていた、無垢で罪無き幼い顔だ。
この肉体の何処に、まる二昼夜郵便局を占拠し、
五人もの男女を射殺した狂気が潜んでいたというのか?
検察でも裁判でも、金欲しさと言う以外、
息子はその動機を一切語らぬまま死刑になった。
しかし、世間並みの暮らしの中で、それなりの小遣いも与え、
無事希望の大学にまで入ったのに、
金の為だけで、あのような凶悪事件を起こすわけがない。
その動機の核心は、
共稼ぎで家を不在にしがちだった親子の暮らしの中にあったのだと、
美代はとうの昔に理解している。
だが、その核心の本質は何だったのだろう。
張りめぐらされたアメーバの輪郭は見えても、
己の慙愧を納得させるにその実像は曖昧すぎた。
そして、とうとうその本質を知る機会は永遠に失われてしまった。
「あんたがそれをわかる女なら、こうしてここに俺はいない」
とでも言うように、棺の中の息子は我関せずの表情だった。
美代にどっと疲れが押し寄せ、
徒労のような自らの人生に膨大な空しさを感じた。
あらゆる力が抜けて弛緩してくる。
「あたしのほうが仏になった気分だよ」
あと二年で古希になる。我が子が生きているうちはと、
歳も忘れ必死に生活してきたが、やっぱり永く生き過ぎた。
もう思い残すことは何もない。
美代は帯の間から、小さくたたんだ一枚の紙きれを慎重に取り出してひろげた。
「チュンチュク すずめがないている」
と、息子に向かって囁いた。
「あの日帰って、あっちこっちひっくり返して見つけました、
あなたの書いたこの詩を。
確か小学二年の時でしたよ。
担任の女の先生、それは誉めてくださり、母さんに贈ってくださった。
でもおそらくこの詩の中に、あなたの闇の始まりがあるんだねえ」
美代は我が子の狭い額をくりかえし撫でまわした。
それから、できる限り自分の唇を息子の耳元に寄せた。
「チュンチュク すずめがないている
みんな なかよく あそんでる
チュンチュク すずめがないている
ぼくといっしょに あそぼうよ」
ゆっくりと、つたない文字の一つ一つをていねいに読んだ。
低く細いその声は、まるで罪深き過去の浄化をうながすように透明であった。
二度繰り返し読んでから、美代は薄く黄ばんだその紙をていねいにたたみ、
経帷子で横たわる息子の胸元にそっとはさんだ。
そのとき、死者の顎下の首にくっきり刻み込まれた縄目の跡が目にとびこんだ。
美代は、その黒く爛れた痕跡をカッと凝視し、
途方もない慄然に襲われ、思わず身を固くした。
無意識に両掌が自らの首を支えていた。
そして堰を切ったように、
あの日からずっと遠くへ追いやっていた人並みの感情が爆発した。
慟哭は幼女のようにわけもなく、涙は泉のようにとめどない。
美代は激しく呻きながら我が子の頸部に両手をあてがい必死で揉みほぐした。
そうすれば縄目のあとが無くなるとでも信じているかのようであった。
幾つもの過去が沸騰し交錯した。
夫婦共に残業になり、
遅い帰宅の玄関口で明かりも点けず剥製のごとく蹲っていた我が子。
留守番のご褒美にお土産で渡したゲームを、受け取ってすぐ足で踏んずけ、
バラバラに壊してしまった我が子。
夏休み、親子で行った市民プールでわざと溺れ、
手足を踊らせ、自ら水中に沈もうとした我が子。
その我が子の首を揉んでいた美代の形相が、たちまち修羅と化し、
両手に恐ろしい力が入った。
力は、屍の我が子の命を再び絶つかのようにどんどんどんどん強さを増した。
甲高い女の嗚咽が、死体搬送車の窓ガラスを貫通し、路上の空気を切り裂いた。
信号待ちの車の列が一瞬乱れ、
そのうちの何台かはノッキングして、軽く宙に浮いた。
やがて黒いワゴンは、平日の人影少ない桜並木をくぐり抜け、
火葬場の中へ、ひょいと吸い込まれた。
完
|
|